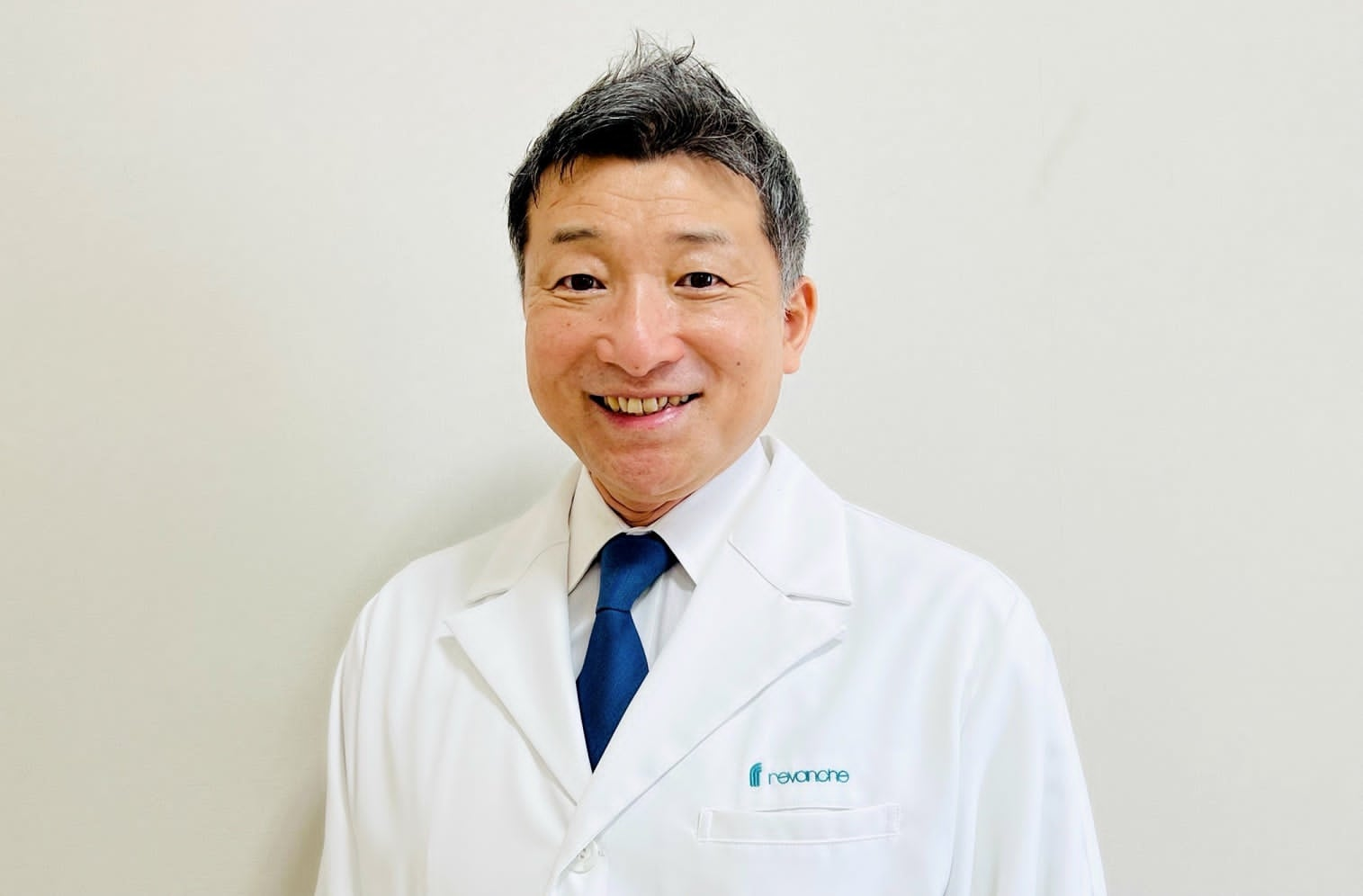
1965年金沢市生まれ。
1984年、父親の経営する食品研究会社に入社後、
大手食品会社の新商品開発などに携わる。
会社方針により、化粧品開発に着手した際、
化粧品原料の安全性に疑問を抱き、
1990年、化粧品メーカーのルバンシュを設立。
「口に入っても心配のない化粧品作り」を目指し自然派化粧品を生み出す。
2011年東日本大震災直後、水を使わず使用できるシャンプーをわずか1ヶ月で開発し、被災地に無償提供を行う。
2013年、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」審査委員会特別賞を受賞。
2016年、「石川県ワークライフバランス企業」優良企業賞を受賞。
■雑誌、書籍掲載
「月刊 商業界」2019年1月号 商業界
「月刊 人事マネジメント」2023年10月号 ビジネスパブリッシング
「日経トップリーダー」2024年7月号 日経BP
坂本光司著「ニッポン子育てしやすい会社」2019年4月 商業界
坂本光司著「いい会社には、活きた社内制度がある」2023年3月 同友館
「人を大切にする経営学 用語事典」2025年5月 共同文化社
――今日は「みずのたまインタビュー」に、株式会社ルバンシュの千田社長にお越しいただきました。まずは自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。株式会社ルバンシュで代表を務めております、千田です。この場所は石川県能美市にあり、化粧品と医薬部外品の製造を行っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
――私もルバンシュさんの化粧品を愛用させていただいているのですが、どのようなコンセプトで作られている化粧品なのでしょうか?千田社長からご説明いただいてもいいですか?
はい。ルバンシュという会社を立ち上げて35年になるのですが、35年前に会社を立ち上げる際、化粧品は肌につけるものですが、手にとってつけるものですから、直接的に体の中に入ることがあります。
そのため、万が一体内に入ってしまっても安全な化粧品を作りたいという思いで35年前に会社を立ち上げました。ですから、ルバンシュのコンセプトは、肌に良いだけでなく、体の中に万が一入っても安心な材料で化粧品を作る、ということになります。
――そのコンセプトに至るまで、といいますか、なぜそのような化粧品を作ろうと思われたのか、少しお話しいただけますでしょうか?
ルバンシュを立ち上げる前に、私の父が経営していた食品の研究会社に勤めていたんですね。そこでは、様々な大手食品メーカーさんの食品開発のお手伝いをする、研究専門の会社でした。ある会社からサプリメントの処方開発を依頼されて、サプリメントを市場に出しました。それが評判が良かったので、「実は今度は化粧品もやりたいんだ」とその会社から言われまして。
当社は食品の研究会社なので、化粧品までは作れませんとお話ししたら、「じゃあ、ちょっと分析装置があるから、お宅に化粧品の分析をしてもらって、食品の研究者としての意見が欲しい」と依頼を受けました。
当時、今もありますが、アロエクリームがとても人気だったんですね。ドラッグストアに行って、色々な会社のアロエクリームが出ていましたので、売れ筋の3商品を買いに行きました。
クリームの蓋を開けてみると、その売れ筋3つとも、クリームに色が付いていたんですね。緑色をしていて、表示を見ると、その緑色を出すために、黄色と青の石油系の色素を使っていたんです。
――そのアロエらしさを出すために?
そうです。アロエが入っているというイメージを出すために。確かにアロエの外観は緑色ですが、絞った液は透明なものですから、あくまで緑色というのは「アロエが入っているよ」というイメージを出すためで。
実際にどのくらいアロエが入っているんだろうと思って分析をかけてみたら、ほとんどアロエが入っていませんでした。もちろんわずかに出てきましたが、それが主成分というほどの量かな、というような量だったのです。
実際にアロエが主成分だという製品なのに、アロエの入っている量が少なかったこと。
さらには、そのアロエが入っているよというアピールをするために色を使っていたこと。
その色は石油系の色素で、これはメイクアップで口紅だったりアイシャドウだったりに色を使うのは分かりますが、スキンケアで色をつけるというのは、その色の成分自体にはスキンケア効果がないので、あくまで商品をよく見せるためだけにそういう色付けをしている。しかも石油系の成分で、ということにすごく憤りを感じて。
当時、全然化粧品の知識がなかったんですけども、なんかこの化粧品業界に一石を投じたいという。当時24歳の頃だったので、その思いがとても、ふつふつと湧き上がってきて。
それで「じゃあ自分で化粧品の会社を立ち上げて、もう一度ゼロから勉強して化粧品の会社を立ち上げよう」と思ったということで、アロエクリームを当時調べた時にいくつか疑問点が出た、というのがきっかけになります。

――それで、自分で化粧品会社を作ろうと思って作られたのが、このルバンシュさん、その社名はどういう意味ですか?
これはフランス語で「復讐」とか「仕返し」という意味です。リベンジのフランス語なんですけども。
リベンジという社名やブランドだとすぐにイメージがついてしまうけども、ルバンシュということだと、なんとなく「ジバンシー」にも似た(笑)、ちょっと響き的には化粧品でもおかしくない名前じゃないかな、ということと、その頃の思いをずっと会社が10年、20年、30年と続く時も、その初心を忘れないということも含めて、思いを名前に付けてみました。ということで、とても気に入っています。
天然原料を真面目に使った化粧品を作りたい。このコンセプトはまあ誰もが認めてくれるとこではあるんです。じゃあこれをどうやって売るのか、と周りに聞かれた時に、やっぱり天然原料って鮮度があるので通信販売をしたいと。
その当時、インターネットって1995年くらいから創成期なんですよね。だから1990年ってインターネットもほぼ普及してないところでしたから、その当時で通信販売でダイレクトにお客様に売るって宣言するのは楽なんですけども、「お前25歳の若造で、工場作るのも借金してやっとやっとなのに、テレビや新聞とかラジオとかそんなところに宣伝をしないと売れない通信販売で商品どうやって知ってもらうんだ」って言われた。
で、それはそうだなっていうことで、お金が貯まるまでは、毎月、金沢駅前のホテルに新製品発表会ということで、そこに友達だとか、その友達の友達とか、親戚だとか、色々な人に来てもらって、毎月発表会っていう場で、商品の説明をさせてもらって、その後帰り際に商品を買っていただく、みたいな、本当にこう端から見ると怪しい販売会みたいにやっていました。
でもそんな方法しかないので、片っ端から金融機関に口座を作って、お昼休みに営業に行ったりだとか、本当にもう泥臭い営業を一人でやってました。
――お一人で?
はい。作るのも作ってましたし、営業も僕一人だったので。当時、僕を入れて4人しかいないので、作るのも営業も僕が、という感じでしたね。
会社を立ち上げて8年ぐらい経った時にですね、能登で大きな地震があって、その年の秋に豪雨があって、という同じ年にダブルパンチがあって。
最初の会社は川沿いにありまして、台風で川が氾濫して、実は会社の中に1mぐらい水が入ってきて製品が全部駄目になって機械も故障して、ということがあって。
その時に友達だとか業者の方が、毎晩、週末はずっと手伝いに来てくれたということがありました。やっぱり社員だけじゃなく、取引先だとか周りの方に助けられた。
実はその1mの浸水がもうやっと片付いたという1回目は8月に来たんですけども、2回目9月にまた同じぐらいの水がつくことがあって、2ヶ月連続です。
だから今の能登も豪雨が来た。そのやっと地震でこう少し落ち着いたところに豪雨が。で、もう完全に心が折れたという。本当にそんな感じだったんですね。
でも本当に、また全部流されてしまって、また自分たちで必死に苦労して綺麗にしたところ、また汚されてしまうともう完全にやっぱり心折れるんですけども。
それでもやっぱりまた同じメンバーが、もちろん社員をはじめ、ちゃんと綺麗にしていくところを皆でやっていって、ということで。
その時にこの人たちをもっと喜ばせなければいけない、やっぱりこれで「大変だったね」で終わるんじゃなくて、社員も「ルバンシュで働けてよかった」取引先だったら「ルバンシュと関わってよかった」と思ってもらいたかった。
本当にその当時でお付き合いくださって、今でもお付き合いもしてます。その当時の社員の中でも今働いている者もおりますし、それがやっぱり僕を強くしたというところがありますね。
――商品作りの信念だけじゃなくて、そこに集まってきた人たちとの絆みたいなものが千田さんを強くしてくれたみたいなところは確かにあるんですね。一人じゃ茨の道だったんでしょうか?
いやいやもう一人だったら間違いなく会社畳んでました。はい、畳んでました。間違いなく大変ですよ。大変です。
だから本当に今年の能登の豪雨の被害のインタビューとかで、本当に当時の自分と重なり合うところもあって、その時の気持ちはとってもよく思い出されるので、そこが一つ、その後色々と社員に対しての福利厚生につながっています。
勤続年数10年で10万円の旅行券みたいな、そういう社員に対しての一つのお礼を言葉じゃなく形にするというところへの発想であるとかっていうところの根本は、やっぱりその2ヶ月連続の1mぐらい会社に水がついた時の、助けてもらったことに対して、会社を通じて返していかなければいけないという思いはやっぱり強いですよね。
――そういう下積みの後、どこかでブレイクスルーのきっかけはあったんですか?
きっかけはここに今「ベジタブルリップ」ってあるんですけども。これは自社ブランドのリップクリームなんですけども、これがブレイクになった。
これ実は10年苦労してお金を貯めて、ようやくその全てが食べられる成分だけで作る化粧品というのを初めて出したのがこのベジタブルリップだったんですね。
社員から「リップって冬場の商品だから、化粧水とかもっと年中使えるものの方がいいんじゃない? せっかく10年かけてやっと溜まったお金で作る商品なんだから」という意見もあったんですけども。
「いや、化粧品が口の中に入る、というのをイメージできる商品はやっぱり、唇に塗る商品が一番。自分が作りたいと思って作ったものがお客さんに響くかどうかというのは、このベジタブルリップで問いたい。で、もしこれでうまくいかなかったらルバンシュを畳む」と社員の前で話をして、この商品を2000年に出したんですね。
そしたらその翌年に、大手の通販会社さんがこの商品に目をつけてくださって、そこの会社オリジナルで同じコンセプトで。ベジタブルリップなんにフルーツの成分を入れて「フルーツ&ベジタブルリップ」ということで、その大手の通販会社さんが採用して雑誌に載せていただいたら、ものすごく反響がありまして。
それでかなり売り上げとそのルバンシュという名前がそこの通販雑誌にも、「食べられる成分で化粧品を作っているルバンシュ」といううちのことも紹介をいただいたので、そんなこともあって、そこで一気に潮目が変わったという感じがしますね。

――すごく人気がある商品なので、もっとたくさん売る、というふうな営業をしようと思ったらできたタイミングもきっとおありだったと思うんですが、この現状の規模でずっと保っていらっしゃるというのは、何か理由があるんでしょうか?
天然原料というのは有限な資源なので、その天然原料を主体とした化粧品を作るという決めた以上は、そもそも、大量生産をやろうと思ってもできないんですね。原料の調達が限られてしまっているので。
そう考えると、規模を追うのではなく、質を追求する。
これは社員に対しても、どんどん社員を入れて、というようなものではなくて、今いる社員と本当に良いものをしっかり作って、お客様に安心してもらう、というスタンスをずっと持ち続けてきているというのは、これは35年間変わらないところはありますね。

――今、白衣を着ていらっしゃいますが、やはり分析とか、データをしっかり取っていくというのがルバンシュの姿勢でもあるんでしょうか?
つい最近なんですけども、ヘアケア商品でシャンプーとトリートメントを製品化しています。実際にシャンプーやトリートメント、特にトリートメントやリンスなのですが、生分解性、つまり使って洗い流した後、それらの成分はちゃんと分解されて環境に優しいのか、と考えた時に、実は化粧品の中でもシャンプー・トリートメント、シャンプー・リンスという分野は、比較的生分解性が劣る製品なんです。
――生分解性が良いというのを謳っている商品も多い気がするんでが?
そうです。でも、実際市販されているもので「この製品のこのシャンプーの生分解性はどのくらいですか?」っていうデータを示している商品ってご覧になられたことあります? ないですよね。
あれだけ毎日使うものですけども、特にリンスやトリートメントは低いんですね。
これは、僕がこの話をするとよく理解してもらえるんですけども。洗い流すのに髪の毛に吸着してトリートメントやリンス効果がしっかり残るということは、成分自体がものすごく強烈で、洗い流してもちゃんと髪にくっついてくれるという、ある種頑固な、強烈な成分なわけですよ。でも、それらは逆に流されていったものというのも、やっぱりそういう頑固な性質というのは変わらないで、やっぱり成分が分解しにくいものなんです。
最近、日本食品分析センターで生分解性を調べたんです。生分解性で「BOD」という指標があります。よく使われるんですけども、「BOD」という指標ですね。これで、そのBODが60%以上だと生分解しやすいという定義になるんです。
シャンプーは70%でした。肝心のトリートメントはというと、ちょっと60%から下がって55%でした。それでも60%に近いところではあるんですけども、今ホームページでは自社のホームページでは、それらのBODの数値も出しています。その60%以下であったとしても、それもオープンに正直にしていまして。
今そのトリートメントは、60%以上になるような改良を今ちょうどやっているところなんですけども。
こういうことって、化粧品って使い心地とかっていうところが、指通りがどうだとか、特に日焼けなんかそっちばっかりに行きがちなんですけども、やっぱり化粧品を作る責任においては、そのものが環境に対してどう影響するのかという、ここが実はすごく欠落しているんですね。
当然そこを追いかけると、今の髪の毛に対しての滑らかさとかツヤとか、そういったところは犠牲にしなければいけない部分も出てくるので、今競い合っている売れ筋でやっているところからすると真逆なところに目を向けなければいけない。他の会社がそこに目を向けていないということもあるので。
でも一般消費者って今この話をした時に、「今自分が使っているシャンプーやトリートメント、リンスというのは本当に環境に対していいんだろうか」って疑問を持ってもらえた時に、その答えを知ることがルバンシュしかできない。ということがとってもやっぱりこの業界の都合の悪いことは伏せておく、というようなところなのかなって。
でもこういうことを言うこと自体も、僕もかなり業界に対してはチャレンジな表現をしてしまってはいるんですけども、でも現実的にはそういったことをもっと真摯に向き合って、数値をオープンにしてくれる会社が増えてくれるといいなとは思っていますね。
――物づくりに対する理念も素晴らしいですが、私が千田社長を尊敬するもう一つの理由は、会社作りの点です。様々な賞も受賞されていますよね。
そうですね。「日本で一番大切にしたい会社」といった賞をいただきました。

――特に驚いたのが、社長が選挙で社員に信任されるというシステムです。その詳細についてご説明いただけますか?
元々、私には息子がいるので、自分が年を重ねたら息子が会社を継いでくれたらいいな、と思っていた時期がありました。
しかし、ある時、地元の大学で「中小企業の魅力」について講演したんです。講演後、学生さんからこんな質問を受けました。「講演はとても良かったです。小規模企業や中小企業の魅力も強く感じましたが、地域の小さな企業さんって、親子で後継をバトンタッチするケースが多いじゃないですか。そういう会社に魅力があって入社しても、もし自分が血縁関係でなければ社長を目指せないというのは、少し閉鎖的だと感じます」と。
その言葉を聞いた時、当時「息子が入ってくれればいいな」と考えていた自分の考えが、いかに浅はかだったかを痛感させられました。学生さんから教えられた形ですね。
確かに会社は、社長のものではなく、社員全員のものです。私の好き嫌いで人選をするのはおかしい、とその学生さんから逆説的に教えてもらったんです。
その時、「どうしたら、このような思いを持つ学生さんにも広く受け入れられる会社作りができるだろうか?」と考えました。ちょうどその頃、石川県の知事選挙の1年前だったんです。新聞やテレビのニュースで「来年の知事選挙に誰が出るか」という話題が出ていて、「これだ!」と思いました。県民が自分の県の代表を選ぶように、社員が自分の会社の代表を選ぶ「社長選挙」にしよう、と。
ちょうど会社を立ち上げて20年目のことでした。私も最初からこのような考えに至っていたわけではなく、様々な苦労を重ね、会社が少しずつ成長していく中で、「これをさらに安定した成長にするにはどうしたらいいか?」と考えていた時に、たまたまその学生さんからヒントをいただいたんです。この社長選挙は、おそらく私にとっても会社にとっても大きな転機になったと思います。
―― 実際にやってみて、怖さはありませんでしたか?
いや、怖かったですよ。開票は投票箱を開けて、社員一人一票ずつ持っていくんです。その場でみんなで開票して、名前を読み上げていくんですが、もし過半数が取れなかったらどうしよう、という不安は常にありました。
初めての社長選挙の開票日の前日には、家族を集めて「もし明日、自分が過半数を取れなかったら、翌年の3月末の決算で社長を辞める」という話をしました。それくらい、私の中ではとても大きな決断でした。
――とはいえ、社長が当然100%信任されるものだと思いますが、実際はどうでしたか?
はい、1回目の社長選挙では満票ではありませんでした。正直悔しい気持ちもありましたが、逆にこの選挙を実施したからには、その「声なき声」である数票、私以外の名前が書かれた票の意見をきちんと吸い上げなければ、この社長選挙をした意味がない、と考えました。
そこで、該当する社員と一人ひとり面談し、その理由を聞きました。そして、その意見を一つ一つ、時間がかかっても納得してもらえるように改善に取り組んできたんです。その結果、2回目以降は今のところ満票で信任されています。
過半数が取れたから良かった、と私がもしも傲慢になっていたら、今のルバンシュはなかったと思っています。やはり、たとえ一票でも、その気持ちに寄り添い、話を聞くという姿勢があったことが、今に繋がっているのだと思います。
――その「質」という意味では、商品の品質もそうでしょうけれども、社員さんたちの質も上がってきてる、という言い方も変ですが、35年で蓄積されているなにかもあるのではないですか?
はい、もちろん僕以上に社員のレベルはどんどん上がってきているので、本当にお客様対応に関しても安心してお任せできます。特にやっぱりクレームがあった時の処理というのは、本当に経験を通して、お客様に怒られる時もありながら、「じゃあどうしたらそのお客様を満足させることができたんだろう」と、必ず反省もセットでやっていきながら、日々改善をしていくことで、お客様に対応ができているのかな、とは思っています。まだまだ完璧ではないですけれどもね。
―千田社長はもう本当に社員さんからも愛されていらしゃりますね。還暦のお祝いのあのコスチュームも!
そうですね。サルの着ぐるみを着て、もうそもそも「サルの着ぐるみを着て還暦のお祝い会に来てください」と手紙に書いてあったのでそれを着て。そこに赤いちゃんちゃんこをプレゼントされて、そのサルの着ぐるみに赤いちゃんちゃんこをした格好で、その後仕事もしてたりもしてたんですけども、はい。
過去にも還暦じゃなくても誕生会というのは必ずやってもらっていて、これまでも着ぐるみは社員からプレゼントしてもらったものもありますので。

―― 千田社長が社員さんに対して、常に心がけていることや大切にしている思いはありますか?
僕は圧倒的に社員第一主義です。社員をぞんざいに扱っていて、「お客様第一主義」はありえません。社員が精神的に満たされていないのに、お客様に対して心からの対応ができるでしょうか。もちろんマニュアル通りの言葉は伝えられるかもしれませんが、それは本当の意味で心からのものではないでしょう。
私は、社長という仕事をしている一社員だと思っています。もちろん代表ではありますが、自分を含め、全ての社員が会社に対して不満がゼロではないでしょう。それでも、トータルで見て「この会社に来てよかった」と思ってもらえるような経営を続けたいんです。
その思いは、たとえば製造部門ならものづくりに反映されますし、お客様対応であれば、お客様と接する際の精神状態に大きく影響してきます。だからこそ、私はお客様の前にいる社員を大切にすることこそが、社長の仕事だと考えています。
以前、友人が「ルバンシュ」という名前は「仕返し」とか「復讐」という厳しい意味にもとれるけれど、私がやっていることは「福が集まる『福集』じゃないか、人が集まる『福集』だ」と言ってくれたんです。まさに、その言葉通りだと感じています。

――今後、千田社長が実現したい夢や希望について教えていただけますか?
先ほどヘアケア商品で洗い流した後の生分解性の話もしましたが、最近、スキンケア全般でナチュラルコスメやオーガニックコスメが本当に増えています。
実は2018年から、これらの製品に実際にどれくらいの自然由来成分が含まれているかを厳格な基準で数値化する動きが日本で始まりました。それが「自然由来指数」というものです。
これはISO(国際標準化機構)という国際的な基準で、企業の国際取引にも影響するほど重要なものなのですが、化粧品においては、ナチュラルやオーガニック製品の自然由来成分の割合が数値化されることになったんです。
2018年にスタートしてから6年も経ちますが、この「自然由来指数」をあまり目にしませんよね? なぜかというと、たとえば当社の製品は「天然由来成分100%」と謳っていますが、この自然由来指数で計算すると、90%になったり、場合によっては80%台になる製品も少なくありません。
2018年に「ナチュラルやオーガニックコンセプトの会社はこの指数を記載していきましょう」という話はありましたが、これは義務ではありません。
例えば、「天然由来成分100%」で販売していた会社が自然由来指数を計算し、90%になったとします。社内会議で「天然由来成分100%」の下に「自然由来指数90%」と記載するかどうか議論になったら、おそらく記載しない選択をするでしょう。
お客様から「なぜ100%と90%で違うの?」と聞かれ、「残りの10%は自然由来ではない成分です」と説明することになれば、「なぜ天然由来100%と書いているのか?」という話になるからです。二つを並べて書くと、かえって不自然になるため、今ではほとんど自然由来指数が表記されていないのが現状です。
――天然由来と自然由来の違い、石油系の成分は天然由来になるのですか?
分かりやすい例で説明しましょう。ご自宅で手作り石鹸を作るとします。植物油を使うとして、石鹸を作るために反応させる苛性カリや苛性ソーダ(水酸化カリウム、水酸化ナトリウム)は、実は石油系の原料なんです。しかし、植物油を使っているため「天然由来成分」であることには間違いありません。
ISOの自然由来指数は、「確かに植物油を使って石鹸を作っているのなら、その出来上がった石鹸の中で植物油を使った部分だけを自然由来指数としてください。そうではない合成の苛性カリを使った部分は、100%から引いてください」という考え方です。
そのため、石鹸製品や石鹸シャンプーでも、およそ80%程度が自然由来指数となり、苛性カリや苛性ソーダの部分がマイナスされる形になります。
実は、化粧品は純粋な天然成分だけで作るのは難しいんです。シャンプーのように泡立つもので、植物性の成分だけで泡立つものはほとんどありません。結局、化粧品は片側が植物性でも、もう片側は石油系の成分を反応させたり組み合わせたりするケースが多いのです。
その点、自然由来指数は「もし片側が石油成分だったら、その石油成分の部分は天然の指数からきちんと減らして表記しなさい」という、非常に真っ当なことを言っているんです。
実は、ルバンシュはこの考え方でずっとやってきました。いくら天然由来と言っても、石油系の原料を使っているものは極力使わない、という方針を元々持っていたんです。
二つの成分を反応させるにしても、少なくとも天然由来の方が有利な、反応したものだけを利用しようとしていました。そのため、当社の社内基準は、世界の自然由来指数とほとんど変わらないレベルだったんです。
2018年からこの指数について勉強し、まさに追い風だと感じました。そしてようやく、資生堂さんが2020年に「BAUM(バウム)」というシリーズで、この自然由来指数を導入してくれたんです。容器に木の素材を使ったりするコンセプトで、「このシリーズは全て自然由来指数を表記しています。全ての製品が90%以上です」と打ち出したことで、ようやく原料メーカーが動き出しました。
自然由来指数は原料メーカーが計算してくれないと分かりませんからね。これまで、一般的にメーカーからの依頼が少なかったため、計算していなかったんです。資生堂さんがそれを先駆けて出してくれたわけです。ただ、資生堂さんでもこの自然由来指数を重視した製品はBAUMシリーズだけで、他のブランドでは一切表記していません。
――これからルバンシュさんが目指すのは、その部分をさらに推し進めるということですね。
その通りです。小さな会社ではありますが、消費者の方々が「ナチュラルコスメが乱立しているけれど、本当にどれがナチュラル成分を使っているの?」と疑問に思ったときに、比較する術がないのが現状です。お客様は結局、セールス文句や企業の信頼性で判断するしかありません。同じ土俵で、世界基準で数値化された基準があるにもかかわらず、その土俵に誰も上がってこない。
だからこそ、私たちは皆にこの土俵に上がってもらいたいと思っています。微力ではありますが、こうした世界基準の指標があることを消費者に知らしめていきたいです。これが消費者の方々が製品を選ぶ基準の一つとして、非常に重要な情報だと思うからです。現在、当社のホームページでは全ての製品に自然由来指数を表記しています。
――本当に一本筋がすっかり通った経営をされていて、尊敬します。
24歳の時に起業され35年やられてきて、振り返ってみて、ご自身の中でずっとここだけは守ってきたルールとか、大事にしてきたものがあるとしたら、どんなことだったんでしょう?
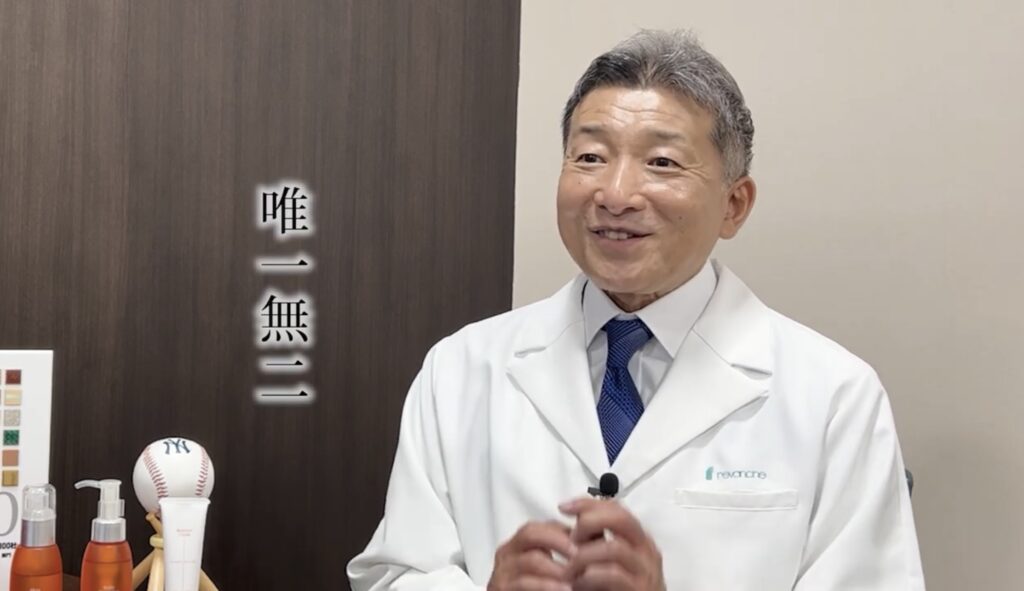
これまでは仕事に関して「化粧品業界の異端児でありたい」というのを、雑誌などのインタビューでよく答えていました。
でも最近、「唯一無二」という言葉がとてもいいなと思ったんです。これは、地元の石川県出身で横綱になった大の里が、大関昇進の口上で言っていた言葉なんですが、私自身も化粧品業界で唯一無二の存在になりたいとずっと強く思い続けているので、非常に心に響きました。
先ほどお話しした自然由来指数をいち早く表記したり、製品が洗い流された後の生分解性の数値を製品に表記したり。そういった、他の化粧品業界が全くやっていないことを率先して行っていく。
これこそが、私がルバンシュであり続ける理由なんだと思うと、大の里の「唯一無二」という言葉が、私の中でとても印象に残っていますね。
最後に一つ、ルバンシュの製品作りを象徴するものを紹介させてください。これは今、私が使っているハンドクリームなんです。少し減っていますが、撮影用に持ってきました。

このハンドクリームは、まさに私がルバンシュで「こんな製品を作りたかった」という思いを形にしたものです。ハンドクリームは手に塗るものなので、塗ったままおやつを食べると、おやつと一緒にハンドクリームの成分も体の中に入ってしまいますよね。この製品は、ハンドクリームとして機能しながら、万が一、口の中に入っても大丈夫なように作られています。
まさに、この製品こそがルバンシュの理念を端的に表していると思い、最後にお見せして終わりたいと思いました。
――どうもありがとうございました。いや、ますますファンになりました!

聞き手:(株)プロ・アクティブ 堀場由美子
株式会社ルバンシュ→式会社ルバンシュ→https://www.revanche.jp/